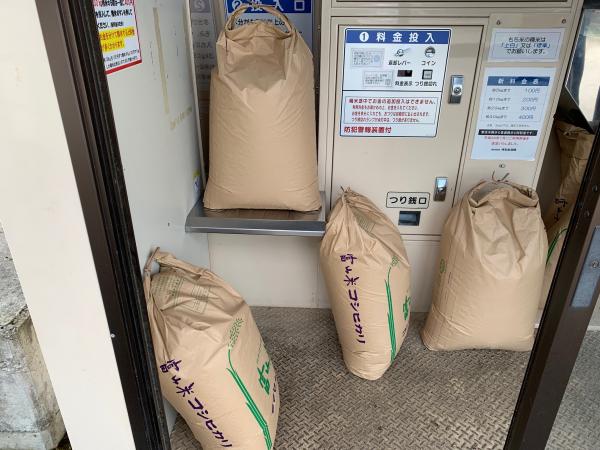二代目「つるぎ」 剣沢二股にて!
続き。
ヘリが飛んでくれなければ、遭難者を安定した場所に固定して暗くなる前に一旦撤収して翌朝警備隊員と戻って収容しようか等々考えたり・・・。
(夜間の救助活動を何度もして来ましたが、助かる見込みのある遭難者の場合です。心肺停止の遭難者を収容するには、夜間の救助作業は危険が大き過ぎるので命が幾つ有っても足りなくなります)
県警ヘリ「つるぎ」からの無線が入り、欅平を通過したとのことだが???しばらくして微かに聞こえて来たエンジン音がいきなり大きくなって、映画「ランボー」の敵の大型ヘリの登場のごとく、折尾谷沿いに高度を上げながら徐々に近づいて目の前に現れたのでした。(若い人はランボー知らないかな???)
こちらの無線にはイヤーフォンを用意していないので、目の前のヘリの爆音で喋るどころか、ダウンウオッシュ(ヘリからの強風)で沢水・木の枝・小石・砂等が舞い上がりまともに目を開けていられないほどです。
馴染みのヘリクルーとは、手の合図とアイコンタクトで意思の疎通を図ります。ヘリは我々の真上10m位でフォバーリング停止。急傾斜の沢の中で、周りの樹木の枝にヘリのローターがスレスレ、近すぎる機体が空を隠して薄暗くなって緊張が高まります。(10m真上でヘリがトラブルを起こした時の事を想像して下さい)
ホイストのワイヤーの先に救助ベルトを着けて下してくれます。救助ベルトを遭難者に装着している間、ヘリはそのままの体制でバックして離れて待機。我々の準備が整ったところで合図を送ると、慎重にまた我々の真上に侵入して来て停止、ワイヤーを上手に手元に降ろしてくれます。フックに救助ベルトを掛けて合図を送ると、そのままバックして離れた空中でホイストを巻き上げて機内に収容したところで「ビューン」と機体を翻しながら下降して、黒部川本流方向に離脱して行く姿がカッコ良くて!
「良かったの~」悪天候の中をギリギリのフライトで来てくれた「つるぎ」に大仏と共に感謝・感謝なのでした。
転落原因は、「傘」をさして歩いておられたそうで、濡れた丸太桟道でバランスを崩してそのまま転落したとのことでした。
山側には手すり番線も張ってあったのですが、手が塞がっていて咄嗟に掴む事が出来ずに残念な結果となったのでした。
昨年も、水平歩道・旧日電歩道で一名ずつの死亡事故が発生してしまいましたが、どちらも恐怖や危険を覚えるような場所ではありませんでした。
「黒部を歩く」には、当たり前のことを守って集中力を切らさずに歩いていただければ、そうそう事故は起こらないはずだと思うのですが。
先のページで「臭い」の話をしましたが、今回も「音」の話をしました。気分が悪くなる方が居られたら申し訳ありません。
脅しているわけではありませんが、人が亡くなるという事!レスキューはかっこいい仕事ではないという事!等を知っていただくことで「慎重な行動で、山を楽しんでいただくこと」に繋がればと思って書いております。