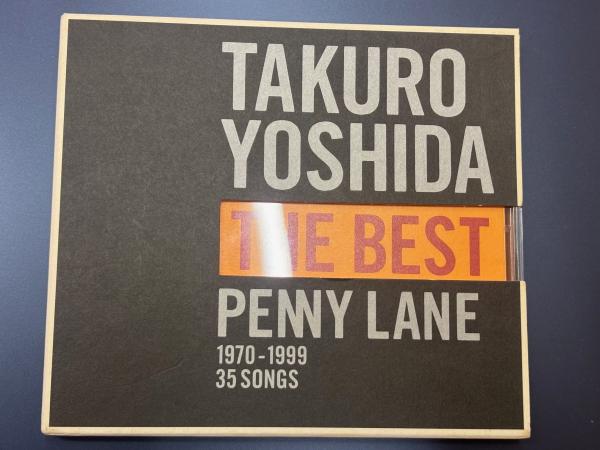勝手に湧いてるように見える温泉ですが、若干ですが利用料が
今日は午後から、富山市内の富山森林管理署へ出向いて毎年2月上旬に開催している山小屋組合と森林管理署の打合せ会の日程調整等の打ち合わせです。
森林管理署は山小屋からしてみれば、小屋敷地・露天風呂敷地・キャンプ場敷地などの「地主様」な訳で、施設の変更・増改築等は届出を行って承認を受けてからになります。
(他にも温泉湧出量・温泉温度等にも利用料が掛かってきます)
今回の災害で、黒部観光旅館組合の多くの施設は営業休止になっておりますが、ありがたいことに森林管理署からは当該休止施設の敷地使用料などの減免処置を行って頂いてます。
ちなみに私がこの業界に入った当時は、奥山の山小屋と森林管理署(旧:営林署)との間で利用料についての訴訟騒ぎ?がありましたが・・・
国立公園の「適正な保護と利用」は、関係者が理解と協力が無ければ成り立ちません!(関係者が多過ぎな気もしないではないのですが・・・また別の機会に)
そういった意味でも各方面毎の会合・打合せは、実情を伝え理解を深め合う機会でもありますので大切にしてゆかねばならないと考えているのです。
って解った様なこと言いながら・・?
実は、今日夕方から富山駅前でヒョンな繋がりの仲間達との年に一度の飲み会が入っているので、森林管理署さんには私が富山に出るのに合わせてもらいました。
今夜は、わざわざ大阪から参加してくれる先輩もおられて楽しみなのですが・・・二日間空けて 20日(埼玉の友人) 21日(地元県議後援会) 22日(ネイチャーポジティブ第4回黒部川流域勉強会)と外せない「飲み会ラッシュ!」が控えており、今回も「ノ・ミカタ」のお世話になることになりそうです。