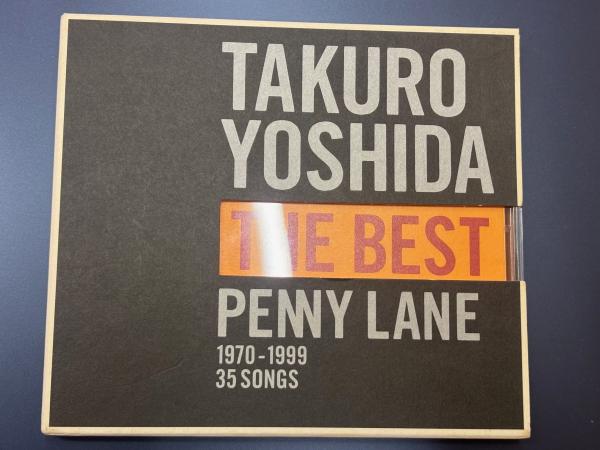富山と言えばブラック?
2025-12-18

話しの種にチャレンジして見られては?
昨夜は久し振りに県庁前の「TAKU」に行くことが出来ました。
人気店なので予約が取り辛いのですが、幹事さんが上手いこと予約を取ってくれて美味しいお酒を頂いて来ました。
店を出るとザーザー降りの強雨でしたが、二次会に「ジェリコ」~「蛭子房」に廻ろうかと思いましたが、あまりの雨の強さに諦めて~最後は相棒と「まるたか屋」に廻って「ブラックラーメン」で〆といたしました。
塩気が強くて血圧高めの小屋主には劇物級なのですが・・・たまに食べたくなり、少しは緩和されるのでは?と言い訳しながら「おろしニンニク」をダバダバ入れて・・・塩辛さを 赤割(赤玉ポートワインの焼酎割りですが、口当たりが良くてグイグイ進んでしまいます)で流し込んで来ました。
ブラックラーメンは確かに塩辛い店が多いのですが、優しいスープのお店も案外多いので、富山に来られて余裕があれば食べ歩きされても楽しいかも?
ちなみに私のお気に入りのブラックは 「大喜 大島店」 車でしか行けない店ですがランチタイムは行列店です。
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2025/12/n20251218a.html