床・壁の材料です。
2019-06-15

順番に調整しながら!
床板は、方向を変えて二重に張ってガタ付きを押えています。
床の高さが微妙に違うと柱が立たず、場所がズレると出入り口の引戸が上手く設置出来ず等々問題が出てきます。
越冬中に、湿気でボワボワに弛んだパネルの交換をしたりと手間が掛っています。(新し目の床板が分かるでしょ)
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190615b.html
2019-06-15

順番に調整しながら!
床板は、方向を変えて二重に張ってガタ付きを押えています。
床の高さが微妙に違うと柱が立たず、場所がズレると出入り口の引戸が上手く設置出来ず等々問題が出てきます。
越冬中に、湿気でボワボワに弛んだパネルの交換をしたりと手間が掛っています。(新し目の床板が分かるでしょ)
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190615b.html
2019-06-15

玄関前の屋根!
名古屋から帰った翌日は、雑務とお土産配りをして火曜日から阿曽原に入って内装・外装工事に入り昨日下山しました。
小屋建ては大人数で「ワーッ」って感じで作りますが、その後は順番・兼ね合い・調整がイロイロあって、間違えて進めて後からエライ目に何度も有っています。全体を把握している大仏が中心となってコツコツと!
建てっ放しの小屋なら、こんな手間の掛かる事しないでで済むのですが・・・。(雪崩の影響が、一番大きな問題なのですが)
そこで、「発想の転換」
この標高で建てっ放しにすれば、小動物の棲家に成る!(ネズミ・カメムシ等)
大掃除でも、行き届かない場所の掃除と思えば!
って考えればいいかと思っています。(前向きに!前向きに!)
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190615a.html
2019-06-10
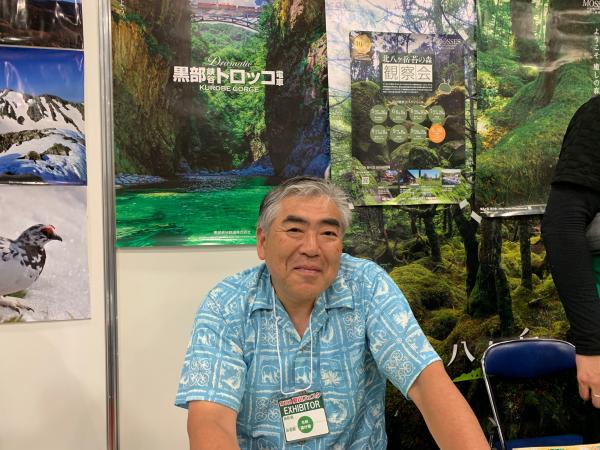
見世物パンダ? すみませんこの後、写真を撮る余裕が無くなりました。実はこのアロハ、雷鳥・ヒグマ・チングルマ等のプリントが、山アロハなのです!
昨日まで、ウインクあいちで開催された「夏山フェスタ」に行ってきました。
初日の土曜日だけで、来場者が5千人オーバーの大盛況で、通路が人で溢れる時間帯も!
中京圏はもとより、大阪から新幹線・横浜から夜行バスで来られたマニア?も・・・。
例年行うパンフの配布は黒部市・峡谷鉄道・観光局の合同ブースにお願いして、私のブースでは解説に特化して説明をしてきましたが、説明中にも「去年お世話になりました」「毎年ここに来ています」とか、見たこと有る様な方々に次々と声を掛けて頂き、更にはHPを見ていて下さる方も大勢おられて持参したDVDも昼には無くなり感謝!感謝!の二日間でした。(7割以上が小屋・夏山フェスタのリピーターの様な?)
今日は、洗濯~お土産を配って~申請文書提出~買い出し等々して、明日からの小屋の内装作り・西仙人山へ雨量計の設置(国交省の仕事)の為の入山に備えねば。
この時期の山小屋はシーズン前で忙しいのですが、来年の「夏山フェスタ」の開催予定日が6月27日28日と遅くなるそうです。
更に忙しくなるはずだから、来年は参加できるだろうか???って声がチラホラ聞こえていましたけど・・・。
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190610a.html
2019-06-06

食堂からの黒部川下流!(中央奥!夏雲の掛った「餓鬼の田圃」が暑そうです)
明日からの名古屋での「夏山フェスタ」で、見世物パンダ?して来ます。
先日からお伝えしているギャラクシー賞受賞作品「沈黙の山」を、自宅コピーしたDVDを取りあえず15枚程度持参して御所望の方に無償配布します。(70分番組)
作品自体も表彰されるほどの力作ですが、阿曽原の小屋建て・小屋締めの様子等も映されております。
いかんせんローカルテレビ局の放送でしたので、見たくても見れない方が居られるのではないかと・・・興味のある方に見て頂けたらと。
数に限りが有りますので、「HP見て来た」と来場して頂けた方に先着順にて配布致します。(営業用じゃないから、法には触れないと思うのですが?)
名古屋近郊の方で、ご希望の方がおられましたら「ウインクあいち」までご来場を!
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190606a.html
2019-06-05

阿曽原谷出合の流れは、川底の石もクッキリ。
明日は、亡父の三回忌。 明後日からは、名古屋のイベントに二泊三日。 週明けからは、小屋の内装工事等々、毎年小屋が建ってからシーズンまでアッと言う間です。
写真は阿曽原谷と黒部川の出合いを、露天風呂の近くから見下ろしたものです。
上流の仙人ダムが水量を絞っていたので、泡立たずに穏やかな流れです。 おかげで、透明度の高い流れが。(先のページの、雪渓から融けたての冷たい水が流れています)
黒部川は、花崗岩が多くて岩・石・砂も、白っぽくて水の綺麗さが映える様な気がします。
8日9日は、週間予報では晴天ではないみたいなので会場は賑わうかも! 今回は、パンフ配りは黒部市・峡谷鉄道・観光局に任せて、説明員に徹して来ようかと。
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190605b.html
2019-06-05

阿曽原谷の残雪は、ドンドン融けていてます。(こんなに早く穴が開き始めるのは・・・)
今年の残雪は、黒部峡谷の様に標高の低いエリアでは残雪が少ないです。(雪崩が出ていない?)
しかし標高の高い所では、尾根の風下側の「吹き溜まり」になる斜面では普段より多いくらいとのことです。
冬期間の降雪量は多くは無かったのですが、風向き・雪崩の発生・春先の悪天候&低気温等々が関係しているのではないかと?(風上側の斜面の積雪は少ない方で、斜面に吹き溜まったまま雪崩れなかった???)
ここへ来ての猛暑で、標高の高い所も融けるペースも上がるのではないかと?
北アルプスの登山道は、夏山では雪渓上を歩く場所が出てきます。 高低差で、残雪の残り方が違うと言う事は、雪渓の状態も普段の年とは違った融け方をするかもしれません。
危険と言う事では有りませんが、何時もの様に最新の情報を山小屋等で仕入れてから歩くことをお勧めします。
この記事の URL : http://azohara.niikawa.com/news/2019/06/n20190605a.html